2023年3月17日と18日に、新日本フィル創立50周年委嘱作品として書き下ろされた小曽根真の新作、ピアノ協奏曲《SUMIDA》が世界初演される。
小曽根といえば、歴史に名を残す一流ジャズミュージシャンたちと共演を重ねてきた、日本を代表するジャズ・ピアニストだが、この20年ほどはクラシック音楽の演奏にも本腰を入れて取り組んできた。とりわけオーケストラと共演する協奏曲(コンチェルト)にかける熱意は尋常ではない。
2017年11月にはニューヨーク・フィルハーモニック管弦楽団の定期演奏会で、指揮者のアラン・ギルバートと共にガーシュウィンの《ラプソディ・イン・ブルー》、そしてバーンスタインの(ピアノ独奏付き)交響曲第2番《不安の時代》を演奏。バーンスタインの長女ジェイミーからも絶賛され、バーンスタイン生誕100周年を祝した3日間のコンサートを大成功に導いた。
そんな小曽根がピアノ協奏曲を書いたのは、これで3回目。第1番にあたるのは、作家・井上ひさしからの依頼で「第18回国民文化祭・やまがた2003」のために作曲された《もがみ》で、2020年にガース・サンダーランドによって管弦楽部分が改訂されている。第2番にあたるのは、2011年にフランスのオーヴェルニュ室内管弦楽団と共演して初演された《JAZZ SUITE》だ。
モーツァルトのピアノ協奏曲第9番《ジュノム》を、2014年に小曽根がビッグバンドに編曲し、それを2019年に兼松衆が管弦楽にオーケストレーションしたコンチェルトもあるが、これはアレンジもの。書き下ろしのピアノ協奏曲としては久々なので、作曲を始める前は緊張したという。
「依頼してくださったのは嬉しかったし、有り難いんですけど、(第2番から)12年振りでしょう? 正直、書けるかなって心配しましたよね。そもそもビッグバンド以外の楽器のために楽譜を書くことに馴染みがないので。2003年に《もがみ》を書いた時、随分勉強したんですけど、あれも後でやり直しましたし……」
何がそれほど小曽根を悩ませたのか?
「ジャズのビッグバンドの場合って、奏者を休ませておくのって失礼なんですよ。それにボイシング(※楽器を重ねて和音にする際の配置)を作っていく時に、可能な限り、他の人が吹いていない美味しい音を吹いてもらいたい。ところが、その考え方はオーケストラだと人数が多すぎて出来ないわけです。それで《もがみ》の時は、かなり悩んだんですよね。でもそれから、色んな作曲家の協奏曲を弾かせてもらって考え方が変わりました。都響でプロコフィエフのピアノ協奏曲第3番をやった時に、トロンボーンの小田桐さんが声をかけてくれて話していたら、彼のパート譜を見せてもらうと休みばっかりだったんですよ。そういう経験を重ねたお陰で、今回は贅沢に休みを書かせてもらいました。吹いてもらわないと失礼!……と思わずに書けたのは、初めてですね(笑)。3回目のコンチェルトにしてやっと、僕も作曲家予備軍の玄関口に近付けたかなって思える曲になりました」
作曲者自身にとっても自信作となったこの協奏曲の副題は“SUMIDA”。このタイトルに込められた意味は?
「新日本フィルのヴィオラ奏者である吉鶴洋一さんが、すみだ郷土文化資料館とか墨田区の色んなところに連れて行ってくださって、この土地の歴史をうかがったんです。そのなかでやっぱり強く印象に残ったのが、今年ちょうど100年になる関東大震災(1923年9月1日)と、東京大空襲(1945年3月10日)のお話でした。焼夷弾で焼け野原になった写真を見たりしているうちに、何か物語のような曲が書けたらいいなと思ったんです」
Part IとPart IIの2部構成となっており、Part Iは「両国 Two Countries」の由来を音楽で描くところから始まる。
「最初に“弦のピッツィカート”が完全5度(で平行に動くモチーフ)で始まるんですけど、これは現在の千葉(下総国)の人たちの声で、その呼びかけに「おーい、はーい」と応える“管楽器”が江戸(武蔵国)の人たち。そして、続く“ハープのグリッサンド”は、この2つの国のあいだに架かる橋なんです。この掛け合いが繰り返される間に色んな人たち(旋律)が登場してきて、ブリッジが何回も架かります。ボーダーレスとかブリッジって、僕がずっと大事に考えてきたことなので、またここでもそういう物語と出会えたなと思いましたね。その後は、ドラム・セットが加わってお祭りのようになってゆきます」
祭りはインタリュード(間奏)を挟んで何度か繰り返されるが、そのたびに雰囲気が変わってゆく……。この展開をどう受け取るかは、聴衆の皆様の想像に任せたいと小曽根は語っていた。そしてPart Iが終わるとオーケストラは休みとなり、ピアノ・トリオ(ピアノ、アコースティック・ベース、ドラム・セット)によるアドリブが挿入される。協奏曲では定番となる緩徐楽章をあいだに置かなかったのは何故か?
「全3楽章にしなかったのは、そうすると第2楽章が悲しみの塊になっちゃう気がして、それが嫌で少し崩したかったんです」
Part IIは単旋律から始まり、まるで人が集まっていくかのように少しずつ音が加わってゆく。
「この作品はこれまで弾いてきたコンチェルトから影響を受けていますけど、Part IIの頭の方での響きはオーケストレーションこそ違いますけどショスタコーヴィチのピアノ協奏曲第1番の第2楽章が怒りを溜めていく感じから貰っていますね。エネルギーを出し切った後にピアノの歌うメロディーが続いていきます。オーケストラとの絡みや、ベース・ソロとピアノ・ソロなどを経て、もう一度Part Iの主題が戻ってくると、ネガティブなエネルギーが変換されて、再生にむかって前へ進んでいくんです」
そして最終的に、どのような結末を迎えるのか? 是非とも、初演の場に立ち会ってご自身の耳で確認していただきたい。結末には小曽根の特別な思いが込められているので、要注目だ!
「僕は若いピアニスト――既にバンドとかやっている角野隼斗くんとかだけじゃなく、藤田真央くんとかにも“是非作曲をして欲しい!”って言うんですよ。(職業として)作曲家にならなくてもいいんですけど、やっぱり自分の曲を書くということはとても大事なことで。というのは結局、チャンスが来たら何がなんでもやるべきです。でも、いきなり出来るようにはならないじゃないですか? 作曲じゃないですけど、僕が最初にクラシックの演奏をするようになった頃とか、心臓が破裂しそうになるくらいけちょんけちょんに酷いことを言っている人がいっぱいいました。自分が弾けていないことも分かっていましたが、結局のところ敵は自分自身なんです。周りの人が何を言おうが、自分の中に確固たるものがあれば関係ないはず。周りの無責任な意見の影響で止めてしまったらそこでオシマイだけど、とにかく練習し続けたことや、色んな経験させてもらえたからこそ、このコンチェルトを書いている時にもここで絶対フルートの音が欲しいとか、フレンチホルンがここで咆えてほしいとかが感覚的に浮かんで来たのだと思います。弾かずに聴いているだけでは、やっぱり分かんないですよ。この20年、僕を信じてチャンスを与え続けてくださった皆さんのお陰で、この作品が出来たと思っています」
クラシック音楽と深く関わり続けた20年を総括する小曽根真の重要作。絶対に聴き逃がすべきではない!
聞き手・執筆:小室敬幸(音楽ライター)
関連公演
小曽根真 プロフィール

1983年バークリー音大ジャズ作・編曲科を首席で卒業。同年米CBSと日本人初のレコード専属契約を結び、アルバム「OZONE」で全世界デビュー。
ソロ・ライブをはじめゲイリー・バートン、ブランフォード・マルサリス、パキート・デリベラなど世界的なトッププレイヤーとの共演や、自身のビッグ・バンド「No Name Horses」を率いるなど、ジャズの最前線で活躍。また、クラシックにも本格的に取り組み、NYフィル、サンフランシスコ響等、国内外の主要オーケストラと共演を重ねる。
2016年には、チック・コリアとの日本で初の全国デュオ・ツアーを成功させ、2017年にはゲイリー・バートンの引退記念となるツアーを催行。また、11月にはニューヨーク・フィル定期演奏会に招かれ、バーンスタインとガーシュインを熱演。このライブ録音は2018年3月、「ビヨンド・ボーダーズ」と題して、小曽根真の初のクラシックアルバムとしてリリースを果たす。
映画音楽など、作曲にも意欲的に取り組み、多彩な才能でジャンルを超え世界的な躍進を続けている。現在、「From OZONE till Dawn」と題した若手音楽家の育成プロジェクトにも取り組み、後進の育成にも努めている。2018年紫綬褒章受章。
2023/2024シーズン(2023年4月~2024年3月)「すみだクラシックへの扉」連続券を発売中
名曲を名演奏でお届けする「すみだクラシックへの扉」シリーズ。一般価格がS席1回券5,000円、A席1回券2,500円のところ、連続券ならさらに20%割引に。
「すみだクラシックへの扉」シリーズでは2023/2024シーズンも引き続き、小室敬幸さんによる「知ればもっとコンサートが楽しくなる! 午前11時の60分ワンコイン講座」を実施します。
※要事前申し込み、500円。演奏会チケットをお持ちの方が対象です。
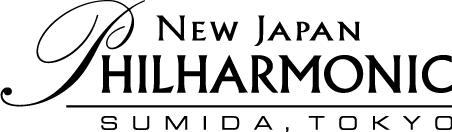


Ayako-Yamamoto.jpg)
