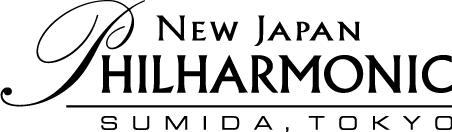第665回定期演奏会を指揮するトーマス・ダウスゴー氏にメッセージをいただきました。
─今回の演奏会では、ブラームスの《ピアノ四重奏曲 ト短調 》を、シェーンベルクがオーケストラ用に編曲した版を指揮されます。もしブラームス自身がこの編曲を聴いていたら、どのような反応を示したと思われますか?
また指揮者として、原曲の室内楽版とシェーンベルクによるオーケストラ版との違いを、響きや感情、演奏へのアプローチの点でどのように捉えていらっしゃいますか?
(ダウスゴー氏)シェーンベルクによるブラームス《ピアノ四重奏曲 第1番》の管弦楽編曲は、まるで二重の時間旅行のようです。
ひとつには、若きブラームスが書いたとしたらどのような響きの交響曲になったのか ― 野性的で自発的な ― を体験させてくれます。そしてもうひとつの時間の方向では、もしブラームスが1937年まで生きていたら、オーケストラのためにどのように書いただろうか、と私たちに考えさせます。要するにこの編曲は、私たちを現実から離れさせ、複数の時代が共存する別の次元へと導く魔法の旅なのです。それは同時に「ブラームスの交響曲第0番」であり「第5番」でもあると言えるでしょう!
通常のブラームスの4つの交響曲は、円熟した、崇高で熟考された作品です。しかし彼の初期の作品の多くでは、より自発的で、野性的で、フィルターを通さず、学校教育的な型にはまっていないブラームスの声が聞こえます ― 例えば《ピアノ協奏曲第1番》や《ピアノ四重奏曲 第1番(作品25)》のように。この時期のいくつかの作品では、彼は楽器編成のさまざまな可能性を模索しており、《作品25》の素材をオーケストラで演奏するという発想も彼の頭をよぎったかもしれません。もしブラームスが1937年まで生きていて、シェーンベルクの試みを耳にしていたら、自分がその可能性に気づかなかったことを少し悔しく思ったかもしれません。
この作品はもちろん優れた室内楽曲ですが、同時に普遍的な響きをもち、室内楽の楽器の組み合わせを超えようとする意志が聴き取れるのです。シェーンベルクは自らをブラームスの自然な後継者と考えていましたが、この可能性を見抜き、シェーンベルクに依頼したのはドイツの指揮者オットー・クレンペラーでした。
シェーンベルクが打楽器を用いたことについては多くの議論があります。しかし、もし彼が打楽器を使わなかったとしたら? それではむしろ時代遅れに響いたかもしれません。実際ブラームス自身も打楽器を使っており、初期の《ハイドン変奏曲》や《ハンガリー舞曲》、そしてもちろん後期の《交響曲第4番》でも使用しています。シェーンベルクは自らの時代に忠実に、ブラームスがまだ用いなかった打楽器や、Esクラリネット、バスクラリネットといった楽器も取り入れました。
シェーンベルクの最終的な目標は、響きの中で明晰さを実現することでした。そしてそれを、この曲が本来室内楽であるという事実から着想を得て、オーケストラをひとつの大きな室内楽アンサンブルのように扱い、さまざまな楽器の音を組み合わせたり分けたりすることで、ブラームスが成し得なかった新しい形の明晰さを追求したのです。
私にとって、この編曲は音楽の精神に忠実に成し遂げられたものであり、その存在に感謝しています。なぜならそれは、ブラームスの若き日の野性味ある姿を交響曲の形で私たちに与えてくれるからです。おそらく、ピアノが弦楽器三重奏を容易に圧倒してしまう原曲よりも、むしろ明晰に響くようになっているとも言えるでしょう。
─ダウスゴーさんは、これまでに2012年3月と2016年1月の2度にわたり、新日本フィルと共演されています。いずれも、シベリウスやニールセン、マーラーといった印象深いプログラムをご指揮いただきました。それからかなりの年月が経ちましたが、今も心に残っていることがあれば教えてください。
(ダウスゴー氏)これまでの訪問での音楽作りには、とても温かい思い出があります。
付け加えると、私が最初にオーケストラに強い印象を受けたのは、1994年にボストン交響楽団のアシスタント指揮者として小澤征爾と共に日本をツアーしていた時でした。そのとき小澤氏は新日本フィルとベートーヴェンの交響曲第2番、そしてボストン響との合同演奏の一部を指揮していました。これまで毎回、私の故郷の音楽(ニールセンやシベリウス)に対する新日本フィルの心を開いた温かいアプローチ、そしてその見事な演奏に特に感銘を受けてきました。本当に素晴らしかったです。
最後の訪問で、もう一つ強く記憶に残っていることがあります――地震です。ある晩、ホテルが激しく揺れて(翌朝もまだ建っていたのは驚きでした!)、別の日にはタクシーに乗っていた時、最初は運転手が突然変な運転を始めたのかと思い、ラジオのスピーカーの調子がおかしいように感じました。すぐにラジオで叫び声が聞こえ、道路が上下にうねり、街灯のポールが道の両側で揺れているのを見て、異変の理由を理解しました。
時差ぼけと重なったこの「地殻の衝突」はとても強烈な体験でした。そのせいか、最初のコンサートのドレス・リハーサルの前に、ホテルであまりに深く眠ってしまい、普段なら起こしてくれるはずの携帯電話のアラーム音にも全く気づきませんでした。リハーサル開始15分前になって、マネージャーが少し心配して会場から電話をくれました。幸運なことに、まだ部屋に固定電話があり、それが十分大きな音を立ててくれたので目を覚ますことができました。その日は、リハーサルに向けて起きて準備するまでの最短記録を更新した日でした!
第665回定期演奏会 2025年9月20日(土)・21日(日)
- ベートーヴェン:ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 op. 61
- ブラームス(シェーンベルク編): ピアノ四重奏曲第1番 ト短調 op.25(管弦楽版)
指揮:トーマス・ダウスゴー
ヴァイオリン:クリスティアン・テツラフ