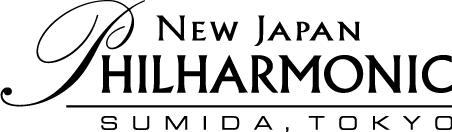20年以上前になりますが、2002年から1年間チェコに留学したことは、とても大きな経験でした。今の自分があるのはそのおかげと思っています。藝大を卒業して、1年間NJPの契約団員をしていた時に、憧れていたチェコ・フィル首席奏者のイジー・フデッツさんのレッスンを2、3回日本で受ける機会があり、その時に「チェコに来られるか?」と聞かれて即答。「日本で学べないことを学びたい!」の一心でした。
日本には、これを練習して、この曲を勉強して……というコントラバスのメソッドがあり、それが伝承されていくのはいいことだと思うのですが、当時の僕には、それとは違う世界も見てみたい!という気持ちが強くありました。楽器の根本的な弾き方や勉強の仕方はもちろんのこと、フレージングや表現など音楽に対する根源的な考え方について、日本で勉強しているのとは違う世界を知りたかったのです。実際、留学して最初に学んだのは、チェコ語のニュアンスやアクセントを演奏に取り入れている、ということ。チェコ語では基本的に単語の頭にアクセントがあるので、「新世界」の演奏でも頭から入ってくるんですね。音価やビートにかかわらず、最初の音にポイントを置くことがチェコの演奏スタイルに影響しているかなと思います。
そして若い時に海外に出てよかったなと思うのは「みんな同じじゃない」と身をもって知ったことです。人がいいと評価するものを真似したり、人に認められようとするのではなく、自分がいいと思ったことを追究するのが大事だと学ぶことができたのは、とてもいい体験になりました。
もともと好きなものに徹底的にこだわるタイプです。子どもの頃は歴史好きでしたが、中学でブラスバンドに入ってコントラバスと出会い、ドヴォルジャークの8番を演奏することになってから世界が変わりました。それまでアメリカン・ロックばかり聴いていたのが、お店が取り寄せてくれたチェコ・フィルのドヴォ8のLPを聴きまくり、「クラシックはこんなに人の心を揺さぶるのか!」と開眼。金沢大学に進みましたが、大学オケで弾くうちに、コントラバスを追究したいと、卒業後藝大に進むことになったのです。
NJPに入団して20年ほど、若い頃は、よくしていただいた先輩方から、そして今は、若い仲間たちから刺激を受けて、勉強し続けていられることに感謝しています。僕にとってのNJPは「攻め」のイメージですから、これからも守りに入らず、音楽的に攻めた演奏を続けていきたいですね。個人的な課題は、楽器を長く弾くための体力作り! 週に2、3回はロードバイクで長距離を走っています。将来的には、故郷の富山で地域の教育活動にも関わることができたらいいなぁと思っています。

(2025年6・7月定期演奏会プログラム掲載)