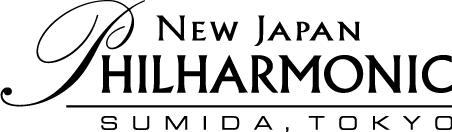アラブ首長国連邦(UAE)の首都・アブダビで毎年開催されている『アブダビ フェスティバル』(Abu Dhabi Festival)。2025年の開幕公演に、佐渡裕指揮 新日本フィルハーモニー交響楽団が出演し、大盛況のうちに2公演を終えました。
アンコールでは、隅田川の桜の美しさを歌った滝廉太郎作曲「花」を、辻田絢菜氏による編曲で演奏しました。英語の曲目解説を音楽評論・渡辺 和氏にご執筆いただき、会場でお配りしましたが、ウェブサイトでは、日本語版を紹介させていただきます。
滝廉太郎:花
◆渡辺 和(音楽評論)
19世紀半ば、今に至る近代国民国家が欧米諸国で形成されつつあるのと時代を同じくして、日本もサムライが統治する江戸幕府から天皇の君主制に則る明治政府が誕生した。江戸幕府崩壊から11年目の1879年、文部省は「音楽取調掛」を設置。五線譜を用いた西洋流音楽教育が始まる。豊後は日出の家老職を務めた武士家系の長男として、皇居の南の中央官庁街となっている旧武家屋敷街に瀧廉太郎(1879-1903)が生まれたのは、正にその年である。明治新政府官僚となった父の転勤で、横浜、富山、大分、竹田と移り住んだのち、1894年には「音楽取調掛」から発展した東京音楽学校に通うようになる。飛び抜けた才能を発揮した廉太郎は、そのまま嘱託教師として学校に残り、声楽曲を中心に作品を発表していく。1901年には日本人初の男子音楽留学生としてベルリンとライプツィヒに学び、爛熟期に至ったヨーロッパ芸術音楽の最先端を経験する。不幸にも結核に罹り、わずか14か月のドイツ滞在で無念の帰国。療養先の大分市内で短い生涯を終えた。
まだ飛行機が人を運び飛び出す前の時代である。廉太郎は、過去の人類が体験したことない距離を移動し、様々な風景を眺め、多くを音楽を聴き、様々な異文化体験をした。凝縮したそんな23年余の時間は、現在判明する限り35曲の音楽作品となって遺された。近代日本が生んだ最初の歌曲作家として、多くが今も愛唱されている。
19世紀最後の年の1900年、廉太郎が21歳の時に「組歌」なる題名で出版した伴奏形態の異なる歌曲集の冒頭に置かれた《花》は、「春のうららの…」と始まる日本人なら知らぬ者はない名曲。新日本フィルが拠点とする墨田区を流れる隅田川の桜花盛りの春風景が描かれ、墨田区民愛唱歌として親しまれている。本日は廉太郎オリジナルの二声とピアノの楽譜を、オーケストラの為に特別に編曲した楽譜で披露される。