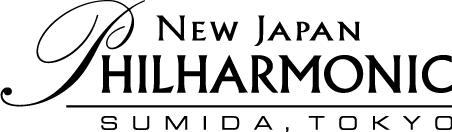この1年で、僕がオーケストラ・プレイヤーとして演奏する基礎を作ってくださった4人の先生方が亡くなりました。NJP元フルート首席奏者の峰岸壮一先生、NJP元ファゴット奏者の中川良平先生、指揮者の飯守泰次郎先生、指揮者の小澤征爾先生です。彼らに二度と会うことができないと思うと本当に寂しいですが、お姿が見えなくなった今も「こういうふうに吹いたら何とおっしゃるかな」と、心のなかで対話しながら演奏しています。
フルートの師匠であり、NJPの創設メンバーの峰岸先生とは、NJPで7年ほど一緒に吹くことができました。先生からよく言われたのは、感じるがままに吹くのではなく、その根拠を考えなさい、ということ。それが演奏に説得力、奥深さを与えることになるのだと。同じことは、中川先生の教えにも通じます。桐朋学園の管楽器の有志でオーケストラのなかでのアンサンブルのレッスンを受けていたのですが、リズム、ダイナミクス、音程に対するノウハウをロジカルに説明くださったことは、今でも僕の財産になっています。
飯守先生との出会いも桐朋学園です。音楽にひたむきで、作品、プレイヤーに対して等しく愛情を注がれる方でした。みんな先生のことが大好きで、普通ピアノで行われる指揮のレッスンのために、有志でオーケストラを組んで参加したこともあります。
小澤さん(先の3人は私にとっては先生でしたが小澤さんは “先生” ではなく親のような、兄弟のような、仲間のような人でしたね)の飽くなき向上心はすさまじく、いい音楽にするための努力を常に惜しまない、求道者のようなところがありました。本番直前までスコアをご覧になって推敲を繰り返され、音楽にちょっとでもいいことがあったらやってみようと僕たちに呼びかけられるパワーに触れられたことは、本当に貴重な体験でした。
1990年4月にNJPに入団して34年、すばらしい先生方と仲間のおかげで、楽しく幸せな日々が続いています。コンチェルトという言葉には「主張し合う」と「協調する」という両方の意味があると言ったのは宮川彬良さんですが、主張し合いつつ協調する、というこの2つが同時に存在するのがオーケストラで、融通しあってひとつのものを作り上げる、本当に美しい世界だと思います。入団する時、父親に「好きな音楽を仕事にするからには、楽しいだけではやっていけないね」と言われたのですが、そんなことはまったくありませんでした(笑)。子どもの時から大好きだったオーケストラを生涯の仕事にすることができて、こんな幸せなことはありません。
恩師たちから常々言われてきたのは、自分たちが教わったことは若い人たちに惜しまず伝えてゆくように、でした。彼らは決して上から圧をかけることなく、僕らの個性を尊重して音楽の仲間として扱ってくれました。いい音楽を作っていくことに貪欲に、前向きな集団であり続けることが、彼らへのご恩返しになるかなと思っています。
(2024年5月定期演奏会プログラム掲載)