去る2007年4月27日、世界的なチェロ奏者・指揮者であり、<フレンド・オブ・セイジ>のタイトルで、新日本フィルに深く関わってくださったムスティスラフ・ロストロポーヴィチ氏が逝去されました。
1984年の初共演以来、指揮者として、ソリストとして数多くの名演を残したくれたスラヴァ。昨年12月は、病をおして新日本フィル定期と特別演奏会のために来日、12月6日の第409回定期演奏会が、最後の演奏会となりました。
12月の2公演でコンサートマスターを務めた崔文洙さん、初共演のときから首席チェロ奏者を務めてきた花崎薫さんに、マエストロとの思い出を語っていただきました。
出席:崔 文洙(チェ・ムンス)、花崎 薫
最後の演奏会
崔 スラヴァはユーモアのある人で、練習中もジョークを言ったりウィンクを送ってきたりすることがあったけれど、12月のときは、最初の練習からそんなゆとりはない感じで、どのセクションにも非常に厳しかったですね。
ときには指揮台を叩いて「そうじゃない!」「ピアニシモと書いてあるのに、なんでそんなにでかいんだ!」と怒鳴ったりしていました。
普段は英語なのに、あのときロシア語の通訳を要求したのは、細かいところまで正確に伝えたかったんでしょう。
残された時間は少ない、伝えられることはすベて伝えたい、という気迫を感じました。
終わったあと楽屋に行って、「またきてください」といったら、「ありがとう、僕はもう来られないと思う」とおっしゃったのは悲しかったです。
花崎 すごく痩せていて、食事もきちんととれないようだったし、手術の痕も痛むようだったけれど、練習が進むにつれて、だんだんテンションがあがって元気になっていったのは驚きましたね。
崔 その後、奇跡的に回復をしたと聞いていたし、あの超人的なスラヴァだから、復活してまた振りにきてくれるだろうと思っていたんですが、残念です。
もっともっと長生きしてほしかった。
サントリーホールでの特別演奏会のゲネプロが終わったとき、「僕からのメッセージだ」として、「もっと楽譜をみて、もっと細心の注意を払って練習をしてくれ」とオーケストラにおっしゃったのが、最後の言葉になりました。
花崎 もちろん僕らだって楽譜をみて、注意して練習しているわけだけれど、そのレヴェルが違うんですね。スラヴァの読譜力は並外れていたし、耳もめちゃくちゃよかった。
これだけの人数のいるオーケストラで、誰がどの音を出しているのか、一人一人がどういう音楽的センスの人なのか、全セクションにいたるまで、すベてわかっていた。
あの人の前に出されると、丸裸にむき出しにされてしまう恐ろしさがありましたね。
花崎 僕はスラヴァが最初にソリストとして新日本フィルと共演した1987年からいますから、彼の演奏、指揮をつぶさに体験することができました。
オケの練習中に、僕の楽器を「ちょっと貸して」と言って弾くことがあったんですが、あれやられちゃうと、なにも言えない(笑)。でもこんな身近で彼の音を聴き、姿、言葉に接することができたのは、なんて幸せだったのだろうと思います。
花崎 思い出はたくさんありますが、忘れられないのが、2001年のリトアニア国立バレエ公演の日本公演のときのことです。
プロコフィエフの「ロメオとジュリエット」のバレエ上演だったのですが、オーケストラ曲としても完成度が高い作品であることを示したいというロストロのアイデアで、オーケストラも出演者として衣装をつけて舞台に乗り、まわりをバレリーナが踊るという、彼流の構成をとっていました。
ところがあの時期、新日本フィルは過密スケジュールで、みんなくたびれ果てていた。加えて、小澤さんが芸術監督をやめられた後で、音楽監督不在の時期だったことも関係していたでしょう。もちろん、どんな状況でも準備を怠ってはいけないことはわかっていたし、精一杯練習していったつもりだったけれど、僕自身も万全の状態ではなかったと認めざるを得ない状態でした。
ロストロがそれを見破らないわけはないですよね。練習の合間に呼び出されて、「クオリティが落ちている。どうなってるんだ」とさんざん説教されました。
その前に共演したとき、とてもいい印象を持ってくださったようで、その後小澤さんの指揮でベルリン・フィルと弾いたとき、小澤さんに「NJPのほうがいいよ」とおっしゃったというエピソードを、あとで僕はロストロにレッスンを受けたときに本人から聞きました。
そのイメージを思い描いて来日し、いざプロコの名作を…と指揮台に立ったら、イメージと違っていた、ということだったんでしょう。ものすごく怒っていたし、また心配してくださっていました。
いろいろ話をしましたが、彼が言ったことは、なにが起ころうと、どのような状況になろうと、「質を落としてはならない」、その一言に尽きるんです。「忙しい」「たいへんな時期」などというのは言い訳にすぎない。ともかく「質を落とすな」と。
崔 僕もあのときロストロと話す機会があって、同じように怒られました。本当は自分たちで気づくベきことだったかもしれませんが、みんな忙しすぎて気づくゆとりがなかった。質を落とす、など、芸術の分野でもっともやってはいけないことのはずなのに。
“クオリティの低い音楽”なんて、あってもなんの意味もないですから。
花崎 あのときロストロさんを怒らせ、失望させてしまったので、実をいうと、あのあともう彼は来てくれないのかもしれない、と思っていたんです。でも来てくれた。
その後2003年に協奏曲を共演していますが、指揮者として次に新日本フィルの指揮台に立ったのが、昨年の12月、最後の公演だったわけです。
まわりの人たちの反対を押し切って、「ショスタコーヴィチの音楽を、日本でNJPと演奏するという使命のために」来てくれたと聞いて、胸が熱くなりました。
崔 ロストロさんに説教された後、なんとかクオリティを上げたいと精一杯頑張ってきて、よくなってきた僕らを聴いてほしい、という気持ちがあった。12月のときは、練習は厳しかったけれど、お説教はありませんでした。そのことについてなにも話しませんでしたけれど、僕らが懸命にやってきたことをわかってくれたのかなと思います。
花崎 ロストロさんが残してくれたことを肝に銘じて、演奏に生かしていくことこそ、恩返しになると思いますし、新日本フィルのさらなる向上につながるはずと信じています。
崔 あのときショスタコーヴィチの8番の練習で、鋭い眼光でぎろっと睨みつけられて、「ピアニッシモ!!」と怒鳴られたとき、ほんとうにいいピアニシモが出せたんです。
これまで経験したことのない音色とバランスだった。僕らもこんなきれいなピアニシモが出せる!と、ほんとうに気持ちいい瞬間でした。
花崎 やっぱりスラヴァの言葉は説得力があるから、みんな真剣にそれに応えようとしますよね。
昔の話になりますが、シモン・ゴールドベルクの練習でも体験したことです。彼も非常に厳しくて、絶対に妥協しなかった。
練習中もたった一言「違う」「もう一度」しか言わないし、同じところを何ベんも何ベんもやらされるので、そのうちになにがいけないのかすら、わからなくなってくる。
けれど、そうやって部分、部分を積み上げていった全体像が、本番の演奏中に初めて見えてくるんです。「ああ、彼はこういう音楽をやりたかったんだな」というのがわかったとき、世界がわーっと拡がってきた。
彼らの頭のなかでは、全体の構造が見えていて、それを作り上げるひとつひとつのタイルが、「こうでなければならない」という確固たる信念がある。そこにオーケストラを近づけるために、何回でもダメだしをするんだと思います。
崔 その信念たるや、「こう思う」というレヴェルではまったくなく、「絶対にこうだ」という、ゆるぎない自信と裏付けに基づいているから、ぶれがないですね。
フィンガリングだって「こうあるベき」というのが出来上がっているから、少しでも違うことをすると、「それはなんだ!」と言って、あの長い手がのびてきて、指差される。特にショスタコーヴィチの場合、スラヴァはじかに知っているし、スラヴァが初演をした曲、スラヴァの助言を受けて書いた曲もある。演奏する曲がどういう状況で書かれたかも、よく知っている。
それだけに説得力がありました。
花崎 彼が一緒に仕事をした作曲家、ショスタコーヴィチ、プロコフィエフ、ブリテンについては、彼らがどういうことを考え、なにをやろうとしていたか、スラヴァはよくわかっているわけで、自分が後世に伝えなければ、という使命感がありましたね。
崔 あのときのピアニシモ、あの音色がいつも出せるようになれば、オーケストラの音色が非常に豊かになると思う。
スラヴァともう会えなくなってしまったいま、僕ら一人一人が、あのときの音を想い起こして、スラヴァが残してくれた宝物として、自分の引き出しにしまっておかなければならないと思います。
崔 あのときショスタコーヴィチの8番の練習で、鋭い眼光でぎろっと睨みつけられて、「ピアニッシモ!!」と怒鳴られたとき、ほんとうにいいピアニシモが出せたんです。
これまで経験したことのない音色とバランスだった。僕らもこんなきれいなピアニシモが出せる!と、ほんとうに気持ちいい瞬間でした。
花崎 やっぱりスラヴァの言葉は説得力があるから、みんな真剣にそれに応えようとしますよね。
昔の話になりますが、シモン・ゴールドベルクの練習でも体験したことです。彼も非常に厳しくて、絶対に妥協しなかった。
練習中もたった一言「違う」「もう一度」しか言わないし、同じところを何ベんも何ベんもやらされるので、そのうちになにがいけないのかすら、わからなくなってくる。
けれど、そうやって部分、部分を積み上げていった全体像が、本番の演奏中に初めて見えてくるんです。「ああ、彼はこういう音楽をやりたかったんだな」というのがわかったとき、世界がわーっと拡がってきた。
彼らの頭のなかでは、全体の構造が見えていて、それを作り上げるひとつひとつのタイルが、「こうでなければならない」という確固たる信念がある。そこにオーケストラを近づけるために、何回でもダメだしをするんだと思います。
崔 その信念たるや、「こう思う」というレヴェルではまったくなく、「絶対にこうだ」という、ゆるぎない自信と裏付けに基づいているから、ぶれがないですね。
フィンガリングだって「こうあるベき」というのが出来上がっているから、少しでも違うことをすると、「それはなんだ!」と言って、あの長い手がのびてきて、指差される。特にショスタコーヴィチの場合、スラヴァはじかに知っているし、スラヴァが初演をした曲、スラヴァの助言を受けて書いた曲もある。演奏する曲がどういう状況で書かれたかも、よく知っている。
それだけに説得力がありました。
花崎 彼が一緒に仕事をした作曲家、ショスタコーヴィチ、プロコフィエフ、ブリテンについては、彼らがどういうことを考え、なにをやろうとしていたか、スラヴァはよくわかっているわけで、自分が後世に伝えなければ、という使命感がありましたね。
崔 あのときのピアニシモ、あの音色がいつも出せるようになれば、オーケストラの音色が非常に豊かになると思う。
スラヴァともう会えなくなってしまったいま、僕ら一人一人が、あのときの音を想い起こして、スラヴァが残してくれた宝物として、自分の引き出しにしまっておかなければならないと思います。
(2007年7月演奏会プログラム掲載)
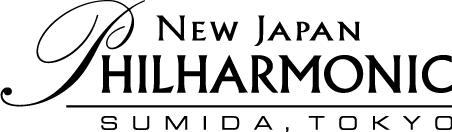


Ayako-Yamamoto.jpg)
